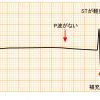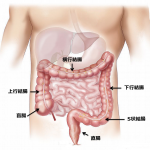シンママナースの マリアンナ です。
近年の超高齢社会に伴い、要支援・要介護認定者の割合は増加。
訪問看護サービスの利用者は急速に増えています。
高齢者の増加に加え、病院での入院日数制限や、介護施設の入居の難しさから自宅での療養が増えていることもその背景にあります。
今後も高齢者の増加に伴い、訪問看護サービスを利用する人はますます増えていくのは確実。
この記事では、寄稿頂いた「訪問看護ステーションの役割と業務」についてお話しています。
訪問看護ステーションとは
訪問看護ステーションは訪問看護を提供する要の施設。
実際はどのような役割や業務を行なっているのでしょうか。
訪問看護ステーションとは、訪問看護事業所のこと。
法律で決められた人員基準を満たし、都道府県知事から指定を受けてはじめて事業を行える訪問看護事業所(訪問看護ステーション)となります。
現在は医療法人や営利法人の開設する事業所が多く、合わせると半数以上に及びます。
訪問看護ステーションの役割
訪問看護は、疾患や怪我などにより住まいで継続して療養を受けることが必要な方に対して、看護師などが診療の補助として療養のお世話をすること。
訪問看護が使える保険制度は2種類あります。
- 介護保険から要介護・要支援者にサービスを提供する場合
- 医療保険から小児など40歳未満の方や疾患などが理由で要介護・要支援以外でサービスを受ける場合
の2種類です。どちらの場合においても、訪問看護サービスを受けるためには医師の指示書が必要です。
訪問看護を利用している方の割合は介護保険利用者が多いのですが、医療保険での利用者も年々増加しています。
入院日数制限の影響や、不要に長期入院していた精神科疾患や神経疾患の方が、居宅での療養に切り替えたことが背景かもしれません。
入院の日数制限により入院の継続が難しいけど医療行為が必要だったり、患者さんの状態が居宅に戻れるくらいには落ち着いて入院は必要ないけれど、居宅で医療行為が必要なケースもあるでしょう。

近年は悪性腫瘍の末期の状態で、最期は最小限の医療行為や緩和医療を行いながら自宅で過ごしたいと希望される患者さんも多い。
そもそも入院が必要でも、色々な理由があり入院や医療機関の受診ができない方もいます。
そのような状況の患者さんが訪問看護のサービスはとても重宝されます。
訪問介護を受けながら住み慣れた場所を変わらず、看護師の処置などの医療的な介入を受けることができます。

訪問看護ステーションは、利用者のニーズと厚生労働省のニーズがすごくマッチしたサービスなんだね。
現在は看護師だけでなく、理学療法士や作業療法士、言語聴覚士も訪問看護ステーションに所属の従事者が増えており、多様なサービスを提供することが可能になってきています。
訪問看護を受けながら在宅で生活できるようになってきた社会背景もあり、近年は精神や行動の障害を有する方も訪問看護を利用するようになってきました。
精神科疾患は長年退院できる状態であっても帰る家がなく、身元引き受け人がいない方も結構います。
数年単位で病院に入院していることが過去に問題に上がりましたが、現在はできるだけ入院は必要最小限にし、居宅へ戻れるよう取り組みがされています。
自宅などの居住場所での看護や医療サービスですから、できることはやはり限られています。
自宅などの居住地で安心して療養ができるよう状態の細かな変化をしっかり確認し、必要ならば入院を勧めたり、必要なサービスの追加を提案したりなど、訪問看護で中心として活躍している看護師は多様なニーズを把握し、サービスを提供していきます。

訪問看護ステーションの業務
サービスを受けている方の疾患や状態にもより、様々なサービスが提供されます。
バイタル測定や状態観察、創傷のケア、ターミナルケアなどの医療行為を医師の指示に基づいて行います。
訪問看護ステーションに勤務する看護師は、訪問看護ステーションに出勤後、カルテから情報収集し一日の行動計画を立てます。
訪問看護に必要な物品は訪問看護ステーションに常備しているので、その日の看護に必要そうな物品をもって、各利用者さんのお宅へ向かいます。
利用者さんのお宅へ移動する方法は、バイク、車、自転車など、ステーションによってさまざま。
数件まわったのち、拠点となる訪問看護ステーションに戻り、その日の患者の状態をカルテに記録します。

在宅看護におけるチーム医療
医師の指示に基づき、理学療法士や作業療法士からのリハビリも受けられます。
嚥下に問題が生じた時や発声に問題が生じた時には、言語聴覚士も参加できチームで訪問看護をして行くことになります。
理学療法士や作業療法士が加わることで専門的なリハビリの時間を作ることができ、病気での安静による二次障害を防ぐだけでなく社会的な孤立も防げます。
孤立しがちな自宅療養ですが、訪問看護を利用することで社会的な孤立を防ぎ、利用者と社会をつなぐ大切な存在にもなりつつあります。
他職種が訪問看護に携わることで、多種多様なサービスが提供できるようになり、ADL支援が一層行えるようになりました。ADLの充実はQOLの向上に直結します。
他職種が関わることで、色々な場面で利用者の心身状態の把握がしやすくなるし、心身の特性を踏まえた日常生活の充実が図れるよう支援を充実させることが可能になります。
訪問看護と聞くと看護師だけしかイメージし難いですが、訪問看護もチーム医療で成り立っているんですね。
自分が住んでいる地域、居住地でできる限り、その方らしく自立した生活ができるよう支援するのが訪問看護の大きな目標と言って良いでしょう。
訪問看護ステーションでは、その方の状態や状況を客観的に判断し、時にカンファレンスを行い評価していきます。
医療行為を含む看護業務は医師の指示がなければ行うことはできないため、医師とのコミュニケーションも大切です。
医師に的確にその方の状態を伝え、必要とアセスメントした経緯をしっかり伝えて指示をもらいます。
病院から居住場所に場所を変えただけで、行う医療行為は限られますが、病院と同じように看護師だけでは成り立たず、患者を中心としたチーム医療を行うのが訪問看護と言って良いでしょう。
参考文献
- 全国訪問看護事業協会
- 厚生労働省資料「訪問看護について」
- 厚生労働省資料「訪問看護の仕組み」
- 厚生労働省資料「訪問看護ステーションの事業運営に関する調査詳細」
- 電子政府の総合窓口「指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準」
- 日本政令索引「指定訪問看護の事業の人員及び運営に関する基準」
- 厚生労働省資料「長期入院精神障害者の地域移行に関すること」