シンママナースの マリアンナ です。
急速な高齢化にともなって、慢性疾患、認知症、看取りなどの多様なニーズに応じた在宅医療の需要が日々高まる一方。
在宅医療には、様々な医療従事者が連携しながら自宅への訪問を行う訪問看護があります。
この記事では、訪問看護を受ける際の手続きに必要な訪問看護指示書について解説していきたいと思います。
訪問看護指示書とは
訪問看護は医療保険と介護保険の公的保険を利用して受けるサービスです。
その際必要となるのが主治医からの訪問看護指示書。
指示書には主治医が診察した上で、疾患名や現在の病状、必要な処置の指示や注意事項などが記載されます。
その指示書にもいくつか種類があり、どの保険を利用するか、患者様がどのような状態でどうゆう訪問看護が必要な中で変わってきますのでこれから説明していきます。
訪問看護指示書
これは最も一般的な訪問看護指示書ですが、保険によって医師の指示期間や対象患者様など、内容が違います。
医療保険を利用する場合
主治医が患者様の診察をもとに訪問看護指示書を作成し、指示書が交付されます。
指示の期間は最長6カ月までとし、主治医が月1回300点まで算定できます。
2か所以上の訪問看護ステーションに交付することもありますが、その場合の算定も1回分となります。
基本的に訪問時間は30分~60分、週に3回程度の訪問になります。
対象は40歳未満の者及び40歳以上の要支援者、要介護者でない患者様、在宅で継続的な療養を受ける状態で通院が困難な場合です。
要介護、要支援の認定をされた患者様は、介護保険の利用をするのが一般的ですが、厚生労働大臣が定める疾病等(末期の悪性腫瘍、多発性硬化症、重症筋無力症、スモン、筋萎縮性側索硬化症、 脊髄小脳変性症、ハンチントン病、進行性筋ジストロフィー症など)の患者様、気管カニューレなどの管理が必要とする患者様、精神科訪問看護を要する患者様、急な状態悪化などで特別訪問看護指示期間におかれている患者様は医療保険利用となります。
介護保険を利用する場合
介護保険の利用では、本人や家族が、主治医に訪問看護の希望を伝え、主治医が必要であると認めた際、居宅介護支援事業所のケアマネジャーがケアプランに訪問看護を組みます。
訪問看護ステーションは、主治医から訪問看護指示書を受けケアマネジャーが作るケアプランに沿って看護師が訪問看護を行います。
介護保険の支給内容に収まるようにプランを作成します。介護保険のサービスを利用するには、住んでいる市町村に申請し、要介護1~5又は要支援1~2の認定を受けていることが前提となります。
対象は、第1号被保険者は、65歳以上で要支援、要介護と認定された患者様、第2号被保険者は40歳以上65歳未満の16特定疾病疾患(がん末期、関節リウマチ、筋萎縮性側索硬化症、後縦靱帯骨化症などの16疾患)の患者様です。
特別訪問看護指示書
医療保険を利用する際に、急性増悪や退院直後など頻繁な訪問が必要となる際には、特別訪問看護指示書が必要となります。
もともと訪問看護指示書が交付されている患者様が対象で、同一の主治医から交付となります。
また、介護保険を利用していた患者様は医療保険へと変更になります。指示期間は主治医の診察から14日間で、月をまたいでも構いません。
原則として月1回の交付で、医師は100点の算定ができます。
気管支カニューレ挿入、真皮までの褥瘡がある患者様は月2回の交付が可能で、毎日の訪問看護を受けることができます。
月をまたいだ場合は、持ち越した指示期間に加えて2回交付ができます。
また、「厚生労働大臣が定める長時間の訪問を要する者」には
「人工呼吸器を使用している状態にある者、(人工呼吸器を装着していない)長時間の訪問を必要とする15歳未満の超重症児・準超重症児、特別訪問看護指示書を受けている者、急性増悪や終末期、気管カニューレ、真皮を超える褥瘡、特別な管理を必要とする患者)の対象者には一回の訪問看護の時間が90分を越える長時間看護、週1回まで(超重症児・準超重症児は週3回まで)」¹
とあり、長時間訪問看護加算として、保険で対応することもできます。
在宅患者訪問点滴注射指示書
週3回以上の点滴必要と認められた場合は、在宅患者訪問点滴注射指示書が必要となります。
指示書の有効期限は指示日から最長7日間までです。月に何回でも交付が可能。
点滴手技の指導などで、週3日以上の訪問を行ってしまった場合でも、在宅患者訪問点滴注射管理料として主治医が60点を算定可能です。IVH(中心静脈カテーテル)は対象外です。
精神科訪問看護指示書
訪問看護ステーションが精神科訪問看護基本療養費(Ⅰ)~(Ⅳ)及びその加算を算定する時に交付されます。
保険医療機関で精神科を担当する主治医が交付できます。月1回300点を算定することができます。
精神科訪問看護指示書の交付を受けた場合、訪問看護指示書は不要です。
精神障害を有する者に訪問し、訪問看護基本療養費(Ⅰ)~(Ⅲ)及びその加算算定の場合は一般の訪問看護指示書の交付が必要となってきます。
厚生労働省が平成28年に出した「訪問看護療養費に係る指定訪問看護の費用の額の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について」によると、「精神科訪問看護基本療養費について。精神科訪問看護基本療養費を算定する場合には、次のいずれかに該当する精神疾患を有する者に対する看護について相当の経験を有する保健師、看護師、准看護師又は作業療法士が指定訪問看護を行うこと」²とあります。
以前の対象者は、自宅で療養している精神疾患で通院困難である患者様で、訪問看護基本療養費(Ⅲ)のみの算定となっていましたが、平成24年に改定され精神科訪問看護基本療養費が新設され、精神疾患の患者様とその家族が訪問看護の対象者となりました。
まとめ
医療保険と介護保険を利用した場合の訪問看護指示書、頻繁な訪問が必要となる際の特別訪問看護指示書、輸液の処置が中心となる患者訪問点滴注射指示書、最後に精神科訪問看護指示書と、対象となる患者様や指示の期間、訪問回数、算定点数など様々な違いがあり多少複雑でもあります。
しかし、様々な疾患を持った患者様、それぞれに多くのケースがあるように、患者様にもそれぞれ理想とする訪問看護、ニーズがあります。
それぞれの患者様に合った訪問看護が受けられるよう今回の説明をお役立て下さい。
参考サイト
引用サイト

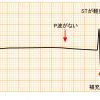












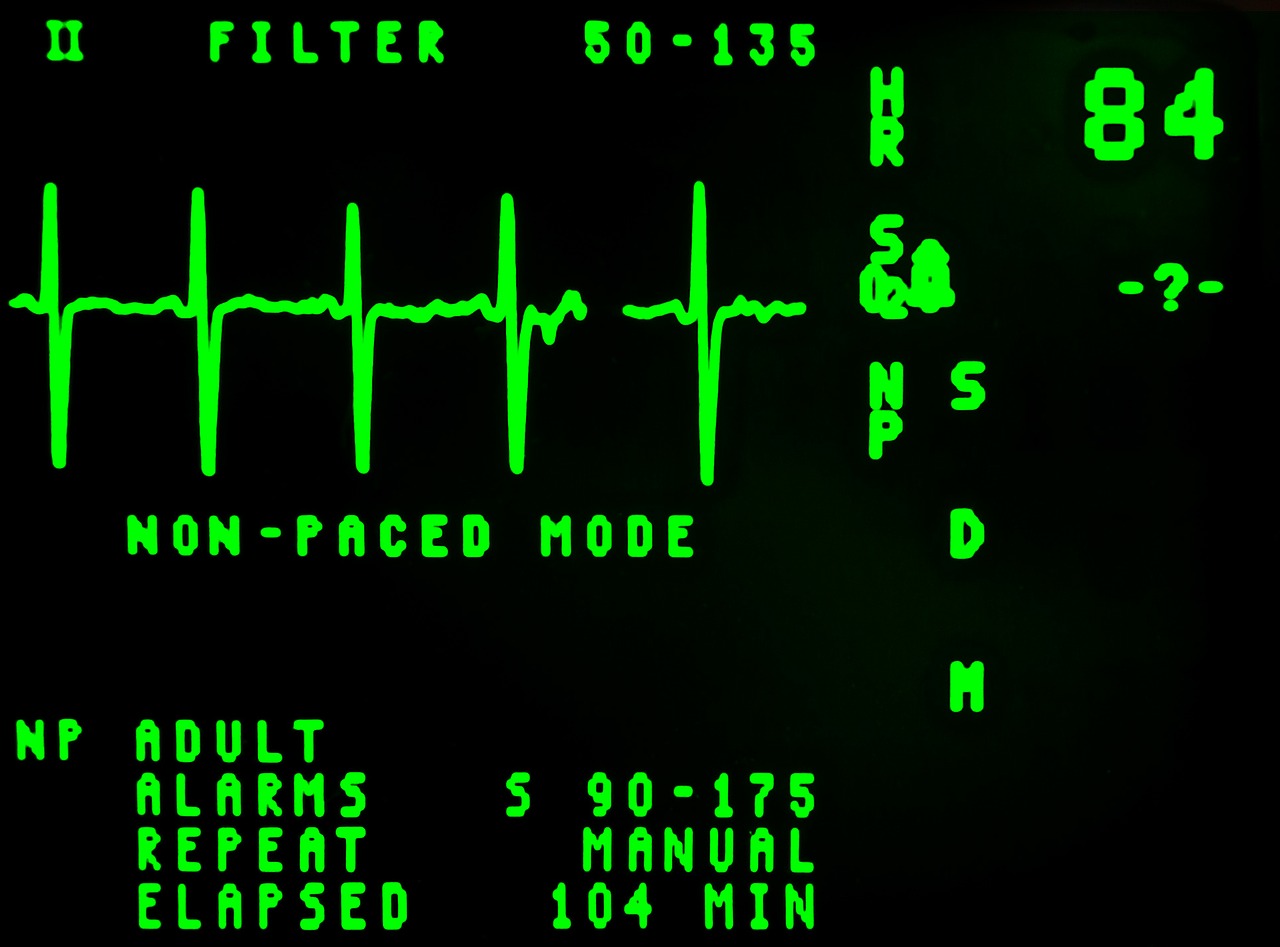

のアイコン-3.png)











